少子高齢化による影響
- 金子 洋樹
- 2025年7月11日
- 読了時間: 3分
暑いですね。夏が始まった感じがします!
日焼けで体中痛いです。今年は結構黒くなると思われます。
今年はBBQ10回以上やる予定があるので楽しんでいこうと思います!
有限会社AT PLUS平社員/株式会社little plus代表取締役 西村です!
さて、今回のテーマは『少子高齢化による影響』について!!
参議院選挙7/20にあるので選挙活動が始まりましたね。
私が今、気になっている党は参政党です。
日本人ファーストを掲げており、少子高齢化対策を行う。
社会保険料、税金が年々上がって理由は少子高齢化だと思います。
会社経営で現状の対策、課題を考えています。

1. 出生率の低下とその背景
まず、少子化の核心的な原因は出生率の低下です。合計特殊出生率は2023年時点で1.2台にまで落ち込み、人口を維持するために必要とされる2.07を大きく下回っています。この低下には以下のような要因があります。
晩婚化・非婚化:女性の社会進出が進んだ一方で、結婚・出産をライフイベントとして選択しにくい社会構造が形成されています。
経済的不安:若年層の非正規雇用や所得格差が広がり、「子どもを持つ経済的余裕がない」という声が増加しています。
育児と仕事の両立困難:保育所不足、長時間労働、企業文化などが子育てを難しくしており、結果として出産に踏み切れない夫婦が多く存在します。
これらはすべて、経営者側の人材確保や福利厚生設計にも影響を及ぼす重要な課題です。
2. 高齢化が止まらない構造的要因
一方、高齢化は医療技術の進展と生活水準の向上によって平均寿命が延びた結果です。加えて、出生率の低下と相まって、人口構造の逆ピラミッド化が進行しています。
医療の進歩:日本の平均寿命は女性で87歳、男性で81歳を超えており、長寿社会が現実のものとなっています。
団塊世代の高齢化:1947年〜1949年生まれの団塊世代が既に75歳を超え、後期高齢者となって社会保障費の増大を引き起こしています。
企業にとっては、年金制度や健康保険料の負担増、シニア層の再雇用制度の整備など、直接的なコストと制度的対応が求められます。
3. 人材確保が最大の経営課題になる
若年層の人口減少により、採用競争は今後さらに激化します。特に中小企業や地方企業は、優秀な人材を採用・定着させることが困難になり、次のような対応が求められます。
働きやすい環境(リモート勤務、副業容認、時短勤務など)の整備
若手だけでなく、シニア人材・外国人・女性など多様な層を積極活用するダイバーシティ戦略
スキルよりもポテンシャル重視の採用へのシフト
優秀な人材が“会社を選ぶ時代”に完全に突入し、企業は「選ばれる組織」になることが生存条件となります。
4. 社会保障・税制負担の増加と企業コストの上昇
高齢者が増える一方で、現役世代が減るという構造は、社会保障制度の財源を企業と労働者に依存させます。
結果として
健康保険料、厚生年金負担が上昇
社会保険料が給与総額の実質的なコスト負担を増大させる
正社員雇用への慎重姿勢がさらに強まる
これに対応するには、業務効率化一層加速し、人的資源の投資先を見極める必要があります。
結論:少子高齢化は“経営の前提”に
少子高齢化は、もはや一部の業界や政策課題ではなく、あらゆる企業にとっての経営前提となっています。人材、顧客、制度、コスト、すべてに影響を及ぼすこの大きな流れに対し、いかに柔軟かつ戦略的に対応できるかが、企業の生死を分けるでしょう。
今後求められるのは、「縮小する市場の中でも生き残れる構造改革」そして「人口減でも利益を生めるビジネスモデルの再構築」です。これは単なる“リスク”ではなく、既存の発想を超えた成長の機会にもなり得ると捉えるべきです。
楽せず、楽しくいきましょう!













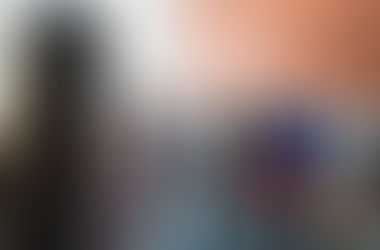







コメント