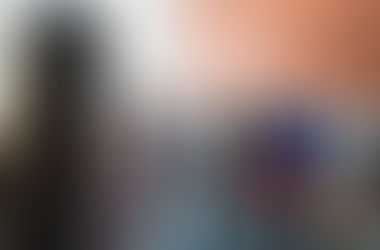インボイスで廃業するってホント?
- 金子 洋樹
- 2022年11月24日
- 読了時間: 4分
人間は考える葦である。
と、どこかの偉い人が言っていました。
きちんと自分で考えて行動できる、ってことですよね。
今日は二日酔いで死んでいます。
二日酔いになるたびに、あんなに飲まなきゃよかった、と後悔するのですが、
なぜ、こんなに繰り返すのでしょう。
人間は考える葦である。
考えはするが、行動が伴うとは限らないのである。
どうも、公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
今回もインボイスについてですが、
制度についての解説ではなく個人的な考察をしていきます。
お題は、
「インボイス制度が導入されることによって廃業が増えるのか」
です。

最近ネットニュース等でもよく出てきますよね。
表現は微妙に違いますが、インボイス制度が導入されることによって、
フリーランスや中小企業の廃業が進む、という論調は同じです。
考察に入る前に、誤解がないようにしたいのですが、
私もインボイス制度自体には疑問がある立場です。
消費税の適正計算が目的であれば、
インボイスを発行するだけでよく、
登録制にする必要はない、との立場です。
免税事業者がインボイス発行のために、
課税事業者になる必要はないと思っています。
その上で、
「インボイス制度が導入されることによって廃業が増えるのか」
について考えていきます。
Aという現象によって、Bという状態に変わる、
ということは、
AがなかったらBにはならない、
ということが成立する必要があります。
ということは、インボイス制度が導入されなかったら、
廃業は増えない、ということを前提とした論調であるべきです。
この点、中小企業白書とかの統計データを見ると、
フリーランスの約4割が1年以内に廃業し、
2年で約半数が廃業、10年後まで生き残れる方はたった1割だそうです。
とんでもない廃業率のようです。
したがって、インボイス制度が導入されることで、
この廃業率があがる、ということのようです。
次いで、インボイス制度によって増加するコストを分析します。
コストが増えるから廃業しちゃうわけです。
基本的に免税事業者が課税事業者になる際のコスト増と同じです。
①益税がなくなる
これはシンプルですね。
今まで免税だったので消費税の納税義務はなかったのですが、
納税しなくちゃいけません。
今まで免税だった=売上高が税込1000万未満です。
ということは、預かっている消費税の最大額は909,090円です。
これがコスト増の最大値になります。
なお、免税事業者の場合、消費税分も含めて所得税と住民税は課税されますので、
とりあえず両方合わせて30%と仮定すると、
270,000円はもともと払っています。
課税事業者になると、消費税分は所得税がかからないので、
差引63万ぐらいがインボイス制度の導入による税金の増加分です。
ただ、これは消費税の仕入税額控除を考慮していませんし、
簡易課税を選択することも考慮していません。
上記を考慮すると実際は45万ぐらいが最大値でしょう。
②申告書を作る
消費税の申告書を作成する必要がありますので、
これを税理士に依頼するとしたら、
数万円はプラスになります。
ここでは5万としましょう。
上記が主なコスト増です。
したがって、インボイス制度で増加するコストは最大で50万です。
月当たり4万ちょっとのコスト増です。
確かに重いですね。
でもそれで廃業しちゃうんでしょうか。
月に4万円増えただけで廃業しちゃう事業って、
そもそも事業として成立してますかね?
月4万円で廃業に追い込まれるのであれば、
事業の改善が必要なのではないでしょうか。
月4万は安くはないです。
ですのでインボイス制度自体はどうかと思っています。
でも月4万で廃業するのは、
インボイス制度のせいではなく、
事業が成立していないせいです。
結果と原因を正しく受け止める必要がありそうです。
「インボイス制度が導入されることによって廃業が増えるのか」
については、
インボイス制度によって廃業するのは、そもそもの事業に問題がある、が結論です。
法律を決めるのは政治家で、
政治家はぼくらが選んでいる(投票しないのも同じ)んです。
ですので、文句を言うなら選挙にいこう。
楽せず楽しく生きましょう。